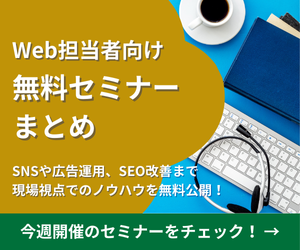Webマーケティングで現状の施策で成果が出ないと、つい新しい施策に意識が向いてしまう。 でも、僕が現場で感じるのは、うまくいかない原因って、案外「今やっていること」にちゃんと向き合いきれていないだけかもしれない、ということだ。
施策そのものが悪いというよりも、それをどう扱っているか。どれだけ踏み込んで検証しているか。 その“踏み込みの深さ”が、成果を大きく左右しているように思う。
グリッド(やり切る力)が弱いままだと、成功も失敗もフィードバックが薄くなり、次の仮説が見つかりにくくなる。
その結果、打ち手がすべて表層的になり、同じ失敗を繰り返す原因にもつながる。
たとえば、こんな“踏み込み不足”が、実は見落とされがちだったりする。
ターゲット設定の曖昧さ:「誰向けか」がふわっとしたまま走り出して、結局誰にも刺さらない。
発信する側の熱量不足:ありきたりな情報発信で、こちらの人となりや熱量、意図がターゲットの目に止まらない。
メッセージの具体性不足:結局ターゲットにとって何が役立つのか、何をしてほしいのか、具体的に伝えきれていない。
これらは、施策の良し悪しではなく、施策の踏み込み方の話である。
こういった部分にしっかり向き合うだけで、施策の見え方も、得られるフィードバックも変わってくると思う。
マーケティングは、ゼロから毎回新しいことを生み出すというより、“うまく複利運用できる仮説”を、少しずつ積み上げていく営みだと思っている。
だからこそ、失敗からもちゃんと学びを拾って、仮説に転換する力が問われる。 「反響がなかった」で終わらせるんじゃなくて、「なんで反響がないのか?」をちゃんと掘る。 それが、次の一手の質を上げてくれるし、成功に向けての近道となる。
「踏み込み」の質を高める3つの取り組み
① 定量だけでなく、定性のフィードバックが得られるようにしておく
- 数字だけじゃなく、リアルな声に触れる仕組みを持つ。
- 定性的なフィードバックも得られるような顧客接点を、日頃から持っておくことも大切。
② チームでの仮説・検証のコミュニケーション習慣を持つ
- 「とりあえずやってみた」で終わらず、「なぜやったか」「どんな結果だったか」「次に何を試すか」をチームで振り返り、PDCAをしっかり回せるようにする。
③ 失敗を前向きに語れる風土をつくる
- 「うまくいかなかったこと」を共有できるチームの方が、強いと思う。
- 小さなチャレンジを積み重ねて、そこから得た学びをちゃんと資産にしていく。
まとめ
成果が出ないときほど、新しいことをやりたくなる。
でも、本当に大事なのは「今やってること」に、どれだけちゃんと向き合えていたか?という視点。
だいたいの仕事の成果は、どんな仕事に取り組んだか、という「中身」ではなく、どんな取り組み方をしてきたか、という当事者の「姿勢」に大きく影響を受けると思う。
中身は都度変えていけばいいけど、姿勢はなかなか変えることは難しい。会社でいうと、組織風土だったり、誰がその仕事に取り組むか、という現場担当者の人選がこの「姿勢」を形作る肝になる。
そこを検証して、改善するだけで、マーケティング施策の成功確率も変わってくるんじゃないかな、と思う。
今やっていることの成果がイマイチ出ていない時、そして何を改善すべきかアイデアがわかない時は、そもそも十分な踏み込みが出来ていないんじゃないか、という点をまず疑うことをおすすめしたい。
【PR】ほぼ毎週、Webマーケティングの無料オンラインセミナーやってます。よかったらぜひ。