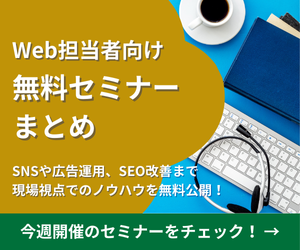ディレクターバンクの事業をはじめて9年目になる。ゼロからはじめた僕自身の仕事も、少しずつ仲間と一緒に動かすフェーズに変わってきた。
そこで僕なりに最近思うことは、「起業」と「経営」は使う筋肉がちょっと違うのかな、ということである。
「起業」とは、そもそも存在していなかった仕事をつくること。
誰にも頼まれていないけれど、「これは必要なんじゃないか」「こんなことがあったら面白いかもしれない」と、自分自身の内側から湧き出てくる発想や動機で始めるもの。
「経営」とは、起業で初めた仕事を継続的、かつ誰にでもできる仕事に仕組み化していくこと。
よく言われることかもしれないが、「起業」は0から1を作るステップだけど、「経営」は1を10や100にするために、誰でもできる仕事に仕組み化して、それを継続的に発展させていくステップ。
「起業」と「経営」という言葉について、いろんな解釈の仕方はあると思うけど、僕的には、そんなふうに解釈するのがしっくりしている。
そして、「起業」フェーズから、「経営」フェーズに移行する際、大切な取り組みに「事業の仕組み化」があるが、ここで大切なのは、今まで自分がやってきた仕事を他の人にもやってもらう時、その楽しさがきちんとシェアできているかどうか、なんじゃないかな、と最近考えている。
みうらじゅんさんの“ない仕事の作り方”で考える「起業」の理想
僕が個人的にとても好きな本に、みうらじゅんさんの『ない仕事の作り方』という一冊がある。
彼は、自分が面白いと思うことを、企画して、営業して、場合によっては接待までして、それを「仕事」として成立させてきた。“一人電通”とおっしゃっているその働き方は、まさに、まだ世の中に存在していなかったものを生み出す行為そのものだ。
僕にとっても、この「ない仕事を作る」というスタンスは、起業の本質の例えとして、すごくしっくりしている。
自分が面白いな、と思うことを、解像度をあげ言語化して、自分で売る。その中で、その面白さを他の人とも共有して、世の中に面白いもの、として成立させていく。
誰でもできることではないと思うけど、これは「ゼロからイチ」を生み出す理想的な流れだと思う。
起業から経営へ。仕事を“誰かのもの”にする仕組み化
自ら起業して取り組み始めた「ゼロ」が「イチ」として、価値を持ち始めたら、今度はそれを「他の人でもできる仕事」に変えていく必要がある。
- 誰かが担えるように役割を設計する
- その仕事がうまく回るように仕組みをつくる
- 関わる人が気持ちよく動ける“場”を整える
それが、事業化。僕が今向き合っているのはまさに、そういった「仕組み化」のステージなんだと思う。
ここから先は、自分の“感覚”だけでは回らない。
だからこそ「いかに他の人にも、その仕事の意味や魅力を伝えられるか?」という視点がとても大切なんだろうな、と最近よく考えている。
仕組み化には「顧客視点」と「働く人視点」の両立が欠かせない
0を1にするのがイノベーションだとしたら、1を10や100にするのはマーケティングの領域だと言われる。
そしてマーケティングで大切なのは、「顧客視点」でコミュニケーション設計していくこと。
そんなマーケティングプランを設計する際に更に大切なのは、その実行体制である「組織」をどうデザインするかである。
「チームとしてどうやって顧客提供価値を提供し続けられるか」という目標に向けて、組織を設計する際、最近だとDX化とかAI化といったキーワードは出てくるのだけど、僕的に一番大切なのは、働く人の視点に立って見た時、その仕事が「やりがいのある業務」に編集されているかどうか、なんだと思う。
このあたりの編集力が、経営者としての力量をはかるポイントになってくる気がしている。
もちろん、人ごとではなく、僕自身にとっても、まさに最重要課題である。
仕事の楽しさをDX化するというコンセプト
世の中的に言われているDX化、とかAI化とか言われている文脈の中では、効率化とか、これで人件費が削減できる、といった趣旨が語られることが多いけど、これは本来の目的ではないと思っている。
これもいろんな解釈はあると思うけど、僕的には、前述した「顧客視点」と「働く人の視点」という両輪を回す、という視点から、DX化とかAI化の本質は、顧客への提供価値の最大化と、それに携わる働く人にとっても仕事をする楽しさを同様に高めていくことなんだと考えている。
なので、経営のKPIとしても、手掛けている事業や仕事の楽しさを、どれだけ多くの仲間と共有できているか?という視点で計れるのかもしれない。
限りのある人生の時間をどんな人達と一緒に楽しむか?そのツールが仕事であり、経営なんだと思っている。
なので、世の中では「DX、AI=業務効率化」のイメージが強いけれど、僕は、「仕事の楽しさ」も仕組み化できないか、ということを考えている。
「この仕事をやると、売上が上がる」とか、「これをやると、お客様から喜ばれる」といった基本的な仕事をする喜びを、再現可能な仕組みに落とし込むだけでなく、もう一段視点をあげて、そんな仕組みを作る試行錯誤自体、「やってる自分が楽しい」と思える仕組みが作れるかどうか。
単に働いている人が、オペレーションをやっているだけでなく、それぞれの人が、前向きに試行錯誤できる環境自体を、大きな括りとして仕組み化している。そんなイメージである。
AIですべてが置き換わり始めた今、人の役目は、誰かから言われた業務をやるだけでなく、個人個人がどんな課題に取り組むべきか?仕事の課題設定力が求められているのだと思う。
試行錯誤をどう楽しんでいけるか?
おそらくずっと試行錯誤だと思うけど、「一緒に働くことが楽しくなる仕掛け」を、僕なりに経営視点で組み立てていきたいと思う。
そして、同じ課題を持っているお客様にも、こういった支援ができるWebマーケティングの信頼できるパートナーとしても、さらに成長していきたいと考えている。
【PR】ほぼ毎週、Webマーケティングの無料オンラインセミナーやってます。よかったらぜひ。